実は曖昧なままになってない?正しく理解したい「ウイルス」や「ワクチン」のこと
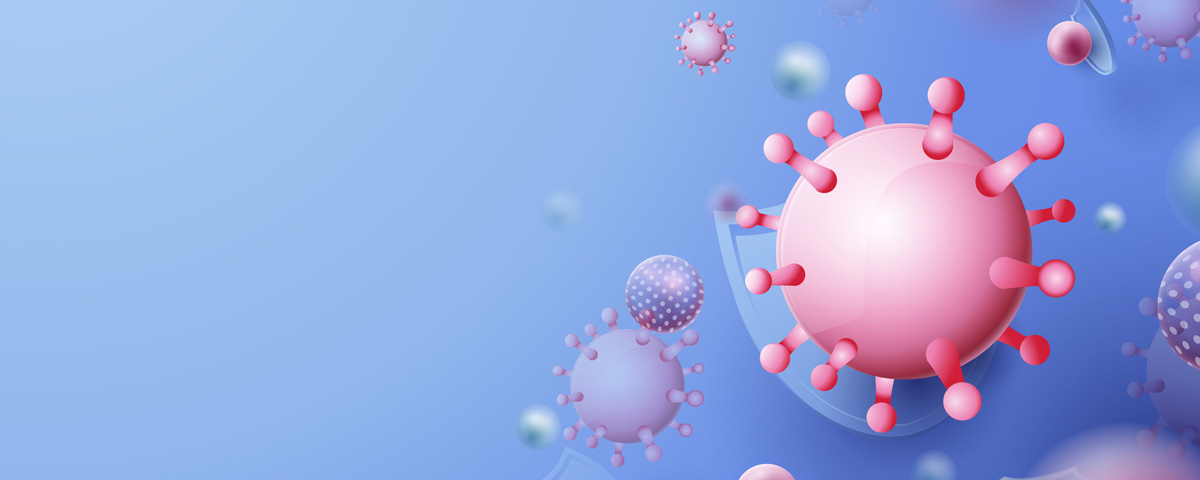
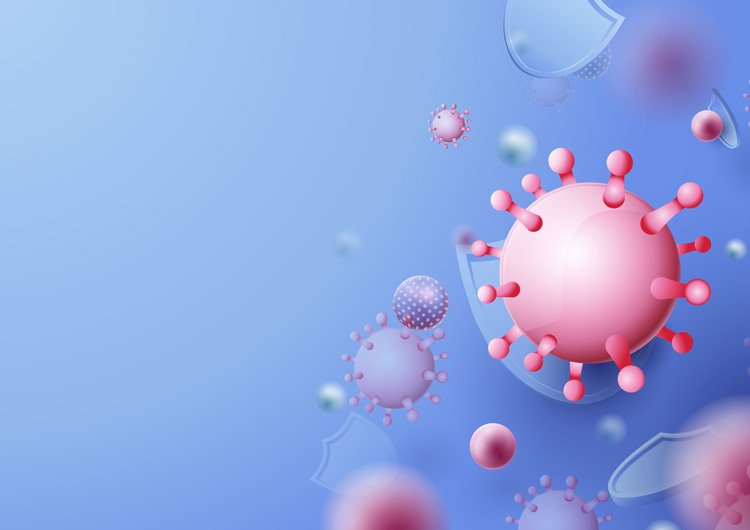
監修:清益 功浩(きよます たかひろ)
ライター:UP LIFE編集部
2021年3月24日
健康
感染症の流行により、連日耳にするようになった「ウイルス」といった言葉。何となくはわかっているつもりでも、「ウイルスとは何か」をきちんと説明できる人は、意外と少ないかもしれません。ウイルスと菌は何が違うのか、またどんな存在なのか。その“基本のキ”をウイルスの研究に携わった経験を持つ医師の清益 功浩先生に教えてもらいました。
そもそも、ウイルスって何?細菌とどう違うの?

どちらも目に見えないほど小さく、生物の体に侵入して影響を及ぼすという印象のある「ウイルス」と「細菌」。似ているようで実は大きな違いがあるそうです。意外と知らないその特徴を清益先生に教えていただきました。
まずウイルスは生物ではない!
「細菌とウイルスの最も大きな違いは、生物であるかないか。細菌は生物ですが、ウイルスは自ら増殖できないので、生物ではないと定義づけるべきです」
「生物か否か」そんな根本的な違いがあるのだとか。さらに両者の構造もサイズも異なっているそうです。
「ひとつの細胞から成り立っている細菌は、核や細胞質などさまざまな要素で構成されています。対してウイルスの構造は、極めてシンプル。DNAやRNAといった遺伝子と、それを囲むタンパク質の殻で構成され、細菌に比べるとサイズもかなり小さいものです。細菌は、栄養源さえ確保できれば、同じ細胞を複製してどんどん増殖していきますが、ウイルスは自ら増殖することができません。細胞を持たないウイルスは、侵入した生物の細胞の中に寄生し、その機能を借りて増殖していきます。つまり宿主がいないと自らも存在できません」
人間や動物に寄生するのがウイルス
自力では増殖せず、宿主の細胞の力を借りることで増えるウイルス。具体的には、どういった生物に寄生するのでしょうか?
「人はもちろん、動物や植物などあらゆる生物に寄生しますが、どの生物を宿主にするかはウイルスの種類によって異なります。よく知られているのは、鳥や豚由来のインフルエンザウイルスでしょう。ただし、ウイルスに感染しているからといって、必ずしも症状が表れるわけではありません。例えば、2009年に流行した豚由来のインフルエンザは、人は発症しても、豚自体が発症することはありませんでした。ウイルスはその種類によって寄生先が異なり、また症状にも差が生じるということです」
私たちはウイルスと共存している
そう聞くと、ウイルスを「遠ざけたいもの」として認知しがちですが、一方で、長い歴史を生物と共存してきたウイルスは、私たちにとって身近な存在でもあるそうです。
「例えば、よく知られている、皮膚に湿疹や水ぶくれができるヘルペスウイルス。これは一度感染すると、体内からウイルスを排除することができません。普段は大人しくしていますが、体の抵抗力が落ちたときに、再び活性化して症状が現れます。体調が悪いとヘルペスがでるというのはこの例にあたります。
またウイルスは悪い面ばかりでもありません。がん治療などに行われる遺伝子治療には、アデノウイルスという種類のウイルスが使われています。簡単にいえば、細胞内へ治療に有効な遺伝子を入れるための運び屋として、ウイルスが活用されているのです。このようなウイルスの極めて特異な性質は、生物の進化の過程においても、密接な関係があった可能性が示唆されています。長い歴史において、生物とウイルスは共存してきたのです」
悪いウイルスに対しては「ワクチン」が必要?「ワクチン」ってどんなもの?

人と共存してきたウイルス。しかし人に悪影響を与えるのは防ぎたいところです。その予防のためには、ワクチンの存在が欠かせません。ワクチンとはどのようなメカニズムなのでしょうか?
ワクチンのメカニズムとは?
「ウイルスの一部を体内に入れ、その抗体をつくることで、病気を予防するのがワクチンの大まかなメカニズムです。現在一般的に使用されているのは『生ワクチン』と『不活化ワクチン』そして『遺伝子ワクチン』があります」
ワクチンの種類はさまざま、身体に入れるウイルスの形状の違い
- 生ワクチン
「毒性を弱めたウイルスそのものを体に入れ、抗体の産生を促すワクチンです。免疫力を高める効果は非常に高く、また長期間効果が持続するのがメリットです。一方で、ウイルスそのものを使用するため、その病気を発症するリスクもゼロではありません。代表的な生ワクチンには、はしかや風疹などが挙げられます」
- 不活化ワクチン
「不活化(感染力をなくした状態)されたウイルスの一部を使ったワクチンです。生ワクチンに比べると、その病気を発症するリスクが低いのがメリットといえるでしょう。ただし、免疫力の持続性が低く、ウイルスの変異効果が低くなるため、インフルエンザワクチンのように定期的に接種する必要があります」
- 遺伝子ワクチン
「遺伝子ワクチンは簡単にいえば、ウイルスそのものではなく、ウイルスの遺伝子を体に入れて免疫をつくるワクチンのこと。ウイルスのタンパク質に関する遺伝子情報を体に送り込み、体内でそのタンパク質を生成することで、抗体ができるしくみになっています。その病気を発症するリスクが低いことに加え、遺伝子を使うことで、効率的に抗体を産生できることがメリットだと考えられています。ただし、新しい手法であるために、長期的な安全性に関しては今後の研究次第といえるでしょう」
ワクチンの副反応はなぜ起きるの?
ワクチンを接種する際に、心配なのが副反応のこと。ではなぜ副反応が起こるのでしょうか?
「まずは、ワクチンを接種するとなぜ副反応が起こるかを理解する必要があります。例えば、注射した跡が赤く腫れたりするのは、皮膚が軽度の炎症を起こしているからです。また、接種後の発熱や痛みなどは、免疫反応の一種です。ただ、時間が経てば改善するケースがほとんどですね。免疫機能が正常に作動していることの表れでもあるので、必要以上に心配することはないでしょう。稀に、アナフィラキシーなどのアレルギー反応が起きる場合もあります。心配であれば医師に相談をし、ワクチンを接種する前にアレルギーに関する問診などを受け、必要があれば皮膚テストを行なってから判断するとよいと思います」
ワクチンだけじゃない!ウイルスの悪さを予防するために心がけるべきこと

風邪などのウイルスを防ぐためには「マスク」「手洗い」「うがい」をして体内にウイルスをいれないことはもちろん有効。それ以外にも「体の免疫力を高めることも重要」と清益先生言います。当たり前のことと思えても、実践できていると自信を持って言える方は多くはないのではないでしょうか?
心がけたい免疫力を高めるための3つの習慣
「まず1つ目は、バランスの良い食事をとること。免疫力を高めるためには白血球の働きが欠かせませんが、その働きを強化し、体内の細胞を増やすために、タンパク質や脂質、糖分、ビタミン、ミネラル、亜鉛といった、さまざまな栄養素をまんべんなく摂取することが大切です。
そして2つ目は、十分な休養と睡眠をとること。疲れていると、体の免疫力は低下してしまいます。ウイルスに負けやすくなって、さらに体調が悪くなるという悪循環に陥らないようにするためにも、無理はせずに、休息をたっぷりと取りましょう。
3つ目は、ストレス・コントロールです。ストレスの程度や原因は個人差が大きいので、自分に合ったストレス解消のしかたを見つけることが大切です。運動が好きなら運動を、インドアが心地良ければ室内でのんびり過ごすなど、ご自身の心と身体がストレスフリーな状態をキープしましょう」
湿度と温度管理で、ウイルスが活動しづらい環境を
またウイルスは細胞に寄生して活動するため、空気をさまよっている状態だと、失活していくものも少なくないそう。室内にいるときは、ウイルスが活動しづらい環境づくりを心がけましょう。
「例えばインフルエンザウイルスの場合、空気中にさまよっている状態で感染力を発揮するのは12~48時間程度。RSウイルスは1~7時間、ノロウイルスは10日前後と、ウイルスによって感染力持続時間はかなり差があります。一方で、多くのウイルスは湿度や温度が高いほど、感染力は低くなると考えられています。例えばインフルエンザウイルスなら、湿度が50%より上回るとウイルスの感染力がグッと下がると言われています。部屋の加湿や室温調整、換気などをこまめにするなど部屋の空気環境づくりも重要です」
外では気をつけていても、自宅で過ごしていると意外と見落としがちなウイルス感染の予防対策。加湿機や、エアコンを上手く使いながら、部屋の空気環境もしっかりと整えましょう。
監修

清益 功浩(きよます たかひろ)
小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤十字社和歌山医療センター、京都医療センターなどを経て、大阪府済生会中津病院小児科・アレルギー科で診療に従事。論文・学会報告多数。診察室外で多くの方に正確な医療情報を届けたいと、インターネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。
2021年3月24日 健康
- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。
